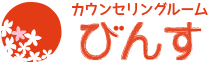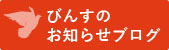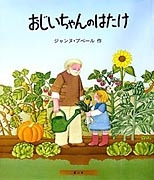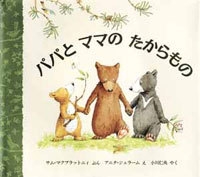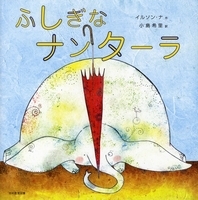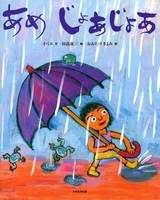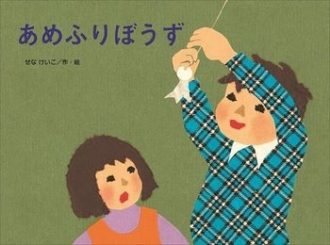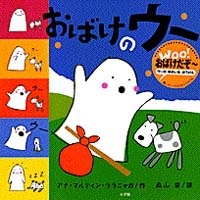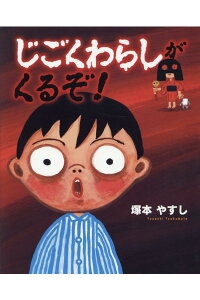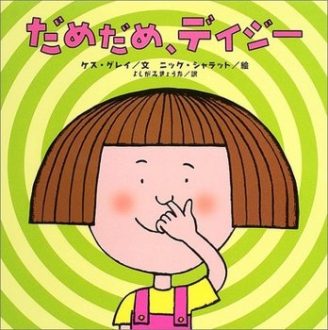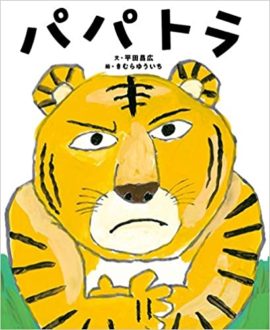季節は廻り、それぞれの役割の中で生きている。
出会いも、別れも大切にしたい。
そんな言葉が浮かんできます。
絵本のどのページからも絵画的な美しさが印象的です。
灰色のローザの・ミールの羽根・アンナの髪・セーターの網目など細かく描かれています。
アンナの家が静かな森の中で、自然の中で季節を感じていることも伝わってきます。
そんな風景やローザとミールとアンナの語りに、心が引き寄せられます。
言葉にできない淋しさ
そして、言葉にしなくても伝わる淋しさがあるという黙ったまま、見送る後ろ姿に、淋しさとローザに対するお別れや応援しているであろうと感じます。
別れと再会が季節と共に繰り返されると感じた絵本です。
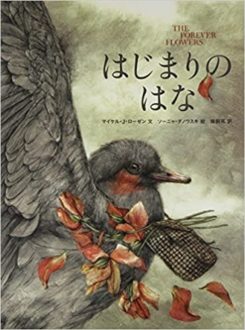
文:マイケル・J・ローゼン
絵:ソーニャ・ダノウスキ
訳:蜂飼耳
くもん出版